- トップページ >
- 最近の解説とハイライト >
- スマトラ沖地震と地球
スマトラ沖地震と地球
北海道大学理学研究科・地球惑星科学専攻・宇宙測地学研究室
email: heki[amark]ep.sci.hokudai.ac.jp
日置 幸介(へき こうすけ)
最近の地球科学的な出来事で世界の注目を集めたのは、昨年(2004年)12月26日に発生して多くの犠牲者を出したスマトラ沖地震とその津波でしょう。それを受けて、インド洋での津波の早期警戒システムの必要性が叫ばれ、新聞やテレビでは津波現象の正しい理解のための特集がしばしば組まれました。スマトラ沖地震は犠牲者が多かっただけでなく、地球物理学的にも1960年代に起こったチリ地震やアラスカ地震以来の真の巨大地震でした。地震が巨大だと、通常の地震では見えにくい様々な現象が観測されます。スマトラ沖地震は人類にとって重大な災害でしたが、ここでは災害から離れてスマトラ沖地震とそれに伴う現象について、地球という星に起きた一つの出来事としてやや遠い視点から眺めてみましょう。
2005年1月21日の朝日新聞朝刊のコラム「天声人語」は、小生の現在の職場(北大)、前の職場(国立天文台)、著書が三点セットで登場する印象深いものでした。本稿ではその文面の主な部分を追いながら解説してゆきたいと思います。
(前略)・・・海抜でいうとエベレストだが、地球の中心からの距離ではチンボラソ山が最も遠い。地心距離といい、それだとエベレストは32位になってしまう。地球が真ん丸ではなく、赤道方向が張り出した楕円体だから、赤道に近い山ほど「高く」なる(『地球が丸いって本当ですか?』朝日選書)▼
『地球が丸いって本当ですか?』は、測地学会の五十周年を記念して企画され、朝日選書から昨年五月に刊行された本です。東大地震研の大久保修平氏を編著者に、静岡大学の里村幹夫氏、国土地理院の飛田幹男氏、そして北大の日置の四人が分担執筆しています。上記のような「トリビア」的なエピソードもありますが、測地学(Geodesy、地球の形、重力、回転やそれらの時間変化、またそれらの測定技術を研究する地球物理学の一分野)を軸として、最新の観測技術と地球科学の話題を、50個の質問・回答の形式で解説した本です。北大生協の書籍部でも売っていますので探してみてください。
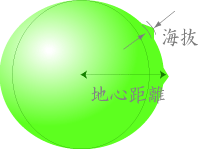
地球の形
単に「形」というと曖昧な概念に聞こえますが、地球の形は「ジオイド」としてきっちりと定義されています。山の高さも地心距離ではなく、海抜すなわちジオイドからの高さで測ります。地球重力場の等ポテンシャル面は無数にありますが、そのうち平均海面に一致するものがジオイドです。海のジオイドは潮汐や波浪や海流などの影響を取り去った海面の形そのものであり、海から離れた地域のジオイドは細い運河を掘って海の水を引いたときの水面の高さになります。ジオイドは球から少しずれて「でこぼこ」しています。でこぼこで最大のものが赤道部分の外側への張り出しです。これは地球の自転で生じる遠心力のはたらきによるもので、地球は全体として南北につぶれた回転楕円体に近い形をしています。地心距離で比べると赤道の近くにある山が高くなるのはそのためです(図1)。他にも地球内部の質量の不均一を反映してジオイドには様々な波長の小さなでこぼこがあります。ただ等ポテンシャル面なので、ジオイドの「山」を越えるのに特にエネルギーを必要とはしません。天声人語の引用を続けます。
▼スマトラ沖地震が地球の形や自転などにも影響を与えたことがだんだんわかってきた。米航空宇宙局(NASA)の発表では、地球の扁平率が減少、ほんの少し丸くなった。また、自転速度が増して一日の長さが100万分の2.68秒ほど短くなった。地軸も2.5センチほど東に移動したという。インドの観測チームによれば、アンダマン諸島はインド本土から1.5メートル遠ざかった。▼
この文章には地球物理学の基本にかかわる事が多く盛り込まれています。地震は、地下にある割れ目(断層面)を境にその両側の岩盤がずれる現象です。断層が地表に達すれば、田んぼの中に突然がけができたり、まっすぐな道が食い違ったりします。断層が海底にあって、海底が急に盛り上がったりへこんだりすることによって生じる波が津波です。沖合で沈み込むオーストラリアプレートによってスマトラやアンダマンなどの陸側のプレートは東北方向に少しずつ押し縮められてゆきます。たまったひずみは地震の断層運動によって解消され、これらの陸地は南西に動いてもとの位置に戻ります。上記の「インド本土から1.5メートル遠ざかった」というのは、正確には東北側にあるユーラシア大陸から遠ざかったというべきでしょう。またここで書かれている「スマトラ沖地震が地球の形に影響を与えた」というのは、単に地震に伴う地殻変動で断層近くの地表が何メートルと変位したことを指しているのではありません。断層運動にともなう地球上の質量の再配分で重力の等ポテンシャル面であるジオイドの形が微妙に変わったことを意味しています。単に海底の形が変わっただけでなく、津波が去ったあともスマトラ沖の海面の高さは地震前とわずかに変わっているはずなのです(ただしmmからせいぜいcmの大きさです)。
地球の回転
地球の形が変わることは、いくつかの波及効果をもたらしますが、ここでは(1)自転への影響(地軸の移動、又は極移動)、(2)扁平率の減少、(3)自転への影響(自転速度の増加)、の三つが挙げられています。物体の慣性モーメントは一般に3 x 3のテンソルで表されることを古典力学で学びます。座標軸を適当に選ぶと対角成分だけになり、物体固有の、直交する三軸(形状軸)周りの慣性モーメント(単位角速度で回転させるために必要なトルク、回転に対する「重さ」)が定義されます。地球は赤道が出っ張った回転楕円体の形をしているので、形状軸の一つである北極と南極を結ぶ軸の周りの慣性モーメントが最大になり、その軸(地軸)を中心に自転するのが安定な状態となります。
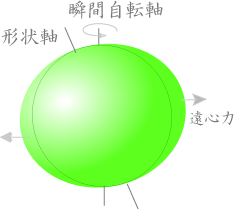
地震が起こって地球の形が突然かわると、その瞬間まで自転に使っていた軸が形状軸でなくなってしまいます。あわてた地球は自転の安定を失い、瞬間自転軸が新たな形状軸のまわりに周期約14ヶ月で回り始めます(図2)。チャンドラー運動とよばれる地球の自由極運動です。オイラーの理論によるとその周期は自転周期と力学的扁平率(慣性モーメントの軸による違いを示す無次元量)の積ですから、計算では地球の場合一年弱になるはずです。でも現実の地球ではその柔らかさや流体核や海のせいで周期が「間延び」して14ヶ月になっているのです。また実際の地球では、地震がおこらなくても大気や海洋などの働きで半径10~15メートルの極運動が常時励起されていますので、スマトラ沖地震の前後でその中心が「2.5センチほど東に」ずれることになります(図3)。現在の宇宙測地技術では地球の瞬間自転軸が地表と交わる位置(極の位置)はミリメートルの精度で求められますから、この地震による形状軸のずれ(極運動の中心のずれ)は一年もすれば確認されるでしょう。
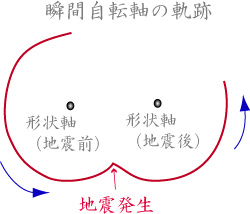
もう一つの波及効果である自転速度の増加は扁平率の減少と関係しています。地球は赤道部分が出っ張った回転楕円体の形をしていることは既に述べました。その程度をあらわす数値が扁平率ですが、これが小さくなると、質量が回転軸に近づく分、地軸の周りの慣性モーメントが小さくなります。慣性モーメントと角速度の積である角運動量(回転の勢い)は保存されますから、慣性モーメントの減少は自転速度の増加をもたらします。スマトラ沖地震による地球の形の変化はたまたま扁平率が減る方向に働いたので、一日の長さが「100万分の2.68秒ほど短く」なったのです。ただし、きまぐれな地球の自転にこの程度の変化は日常茶飯事です。例えば西風が強くなると自転が幾分遅くなるといった具合です(大気と固体地球が角運動量を交換しあっているのです)。自転速度が変わると位相のずれが累積してゆきます。現在の世界時のきまりでは、時間の標準であるセシウム原子時計の刻みと地球の自転の刻みのわずかなずれを吸収するために、時折「うるう秒」を入れて一日の長さを一秒長くして調整します。これは普通年に一回程度ですが、自転が遅め(速め)のときは二回(ゼロ回)になります。スマトラ沖地震の後は「うるう秒」を入れる頻度が幾分少な目になるはずですが、この程度の変化では我々が気づくレベルにはなりません(あらたに「うるう秒」を入れるためにはその千倍、すなわち3ミリ秒程度一日の長さが短くなる必要があります)。地球の形の変化が自転速度の変化では検出できないのに、極位置の変化だと観測できるのはなぜでしょうか。それは前者が巨大な量である地球の慣性モーメントそのものを変化させることであるのに対し、後者は慣性モーメントそのものでなく軸によるわずかな違いで決まる形状軸を動かすことだからです。
地球の振動
さらに天声人語の引用をつづけましょう。地震に伴う地球の形や慣性モーメントの変化は恒久的なものですが、次は一過性(八過性?)の振動に関する話題です。
▼地震波は地球を少なくとも5周し、8周に至っているかもしれない、とは北海道大の解析だ。発生から3週間ほどたっても地球が震えていることを観測したのは国立天文台水沢観測所で、0.3ミリの幅で伸び縮みを続けたという。▼
「北海道大学の解析」とは当専攻グローバル地震学研究室の吉澤博士によるものです。断層がずれると、縦波(P波)や横波(S波)が岩盤中に放射されます。岩盤の中を三次元的に伝わるこれら実体波より、地表に沿って二次元的に伝わる表面波(図4)は一般に長命で、大地震のあとに地球を何周も回るのが観測されます。日本を最初に通過したスマトラ地震の表面波による変位の振幅は数cm程度で、周を重ねるに従ってだんだん小さくなっていきます。以前にこのような巨大地震が発生した1960年代とは、地震計の性能(感度、周波数帯域、ダイナミックレンジなど)もネットワークの充実度も格段に向上しているのですが、地球を8周もする地震波を見たのは地震学者たちも初めてだったようです。
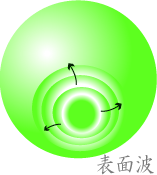
地震に伴う振動でさらに減衰の小さな(Qの大きな)現象が、地球全体の自由振動です。宇宙空間に浮かぶ地球が、まるでお寺の釣鐘のように、その大きさと弾性定数で決まった周期で地震の後に震え続けるものです(図5)。寺ごとに釣鐘固有の「音色」があるように、地球の自由振動も、基本波にさまざまな高調波が重なった微妙な音色をもっています。残念ながら、地球が大きいためこの妙なる音は低すぎて(最も基本的なモードの一つである0S2成分の周期はおよそ50分)、それを「聴く」ためには耳ではなく特殊な装置が必要です。
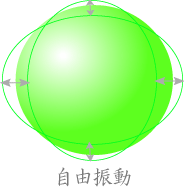
場所や時間による重力の違いを測定する器械が重力計ですが、ngal(十億分の一gal、ちなみに地表での重力はおよそ980 gal)の計測精度を誇る超伝導重力計は現在最も高精度なものです。岩手県の国立天文台水沢観測所は筆者が北大にくる前に勤めていた所ですが、付属施設として北上山地の花崗岩体をくりぬいた江刺地球潮汐観測施設があります。そこに超伝導重力計が設置されており、月や太陽の引力(潮汐力)による重力変化だけでなく、潮汐力に対する固体地球の弾性応答に伴う重力変化や、海水の移動や流体核の動きによる重力のわずかな乱れを日夜記録しています。地球の自由振動は、トンネルに水晶棒を横たえたひずみ計や、広帯域地震計などでも観測できますが、自由振動にともなう加速度を重力計で観測する手法が歴史も古く一般的です。「発生から3週間ほどたっても地球が震えている」のを観測できるのも、スマトラ沖地震の大きさと超伝導重力計の高感度のなせるわざです。
超伝導重力計は最近いくつかの重要な発見をしました。そもそも地球の自由振動は大きな地震が発生したときだけ励起されると思われていたのですが、超伝導重力計の観測によって地震のないときでも小さな自由振動がいつも起こっている(「背景自由振動」)ことがわが国の研究者によって見出されて話題になりました。地球という釣鐘をいつも小突き回している犯人は大気と考えられており、その裏づけ捜査が進んでいます。また2003年秋の十勝沖地震の際は断層のずれによる重力の1μgalに満たない恒久的な変化が、超伝導重力計で初めて見出されました。
地球の気持
さて天声人語の続きはどうなっているでしょうか。
▼激震は人々に苦痛と悲しみをもたらしただけでなく、地球を揺さぶり、衝撃を与え、変形をもたらした。地球自体がなお激痛にあえいでいるかのようだ。・・・・(後略)
ここでは地球を擬人化して「なお激痛にあえいでいる」と主観的に想像していますが、地球物理学者としてはいささか違う感じがしないでもありません。最後の章では地球になり代わってこちらも主観的に想像してみましょう。
スマトラ地震で海の水をビルの高さに持ち上げたエネルギーはどこから来ているのでしょう。そもそも断層で岩盤をずらす地震はなぜ起こるのでしょうか。爪が伸びるくらいのゆっくりとしたプレートどうしの動きが、何十年何百年とかけてプレートの境界の近くにひずみエネルギーを溜めてゆきます。それが一気に解放されるのが地震です(注:それほど一気でない「ゆっくり地震」というのもあります)。そのプレートを動かす力は地球内部に熱対流を起こす力、つまり場所による温度の違いからくる浮力です。さらに突き詰めると、熱対流は地球が自分自身を冷やそうとする過程の一つです。プレート運動や地殻ひずみなどから構成される、地震の「犯罪グループ」の真の黒幕は、地球自身の「熱」といえそうです。
はるかな昔、宇宙空間のちりやガスが自己重力で縮んで太陽系が生まれました。微惑星が合体する過程で膨大な重力エネルギーが解放されたため、生まれたての地球は表面が溶岩の海で覆われる高温の世界でした。誕生以来地球は冷えていきましたが、今にいたる道筋は単純ではありません。地球内部にはウランやトリウムなどの放射性壊変というもうひとつの熱源があるからです。結局地球は、表面で失う熱と内部で発生する熱をバランスさせて、ある定常状態を保つようになります。どのような状態でバランスがとれるかには、天体のサイズが効きます。大雑把な議論ですが、表面から宇宙空間に失われる熱は表面積(半径の二乗)に比例し、放射性の熱源は体積(半径の三乗)に比例します。その結果大きな星ほど、表面の熱流量が大きく内部温度が高い状態を保っています。同じ頃に高温で生まれた地球と月を比べてみると、サイズの小さい月が早く冷えて火山活動も終わっているのが、地震や火山で今もにぎやかな地球と対照的です(ただし月でも最深部ではまだ流体核がうごめいているとの説が有力)。
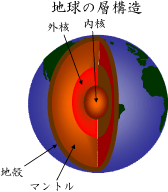
地球の深部は鉄が溶けるほどの高温です。体積で地球の九割ちかくを占めるマントル(図6)は固体ですが、高温では粘性流体としての性質が強くなり、力をゆっくり加え続けると流動します。その結果、中が熱く外が冷たい地球のマントル中で熱対流が生じます。対流するマントルと冷たい外の空間のはざまにできる熱境界層がプレートで、冷えて流動性を失った厚さ百キロ程の硬い岩盤がその実体です。表面で十分冷えた海洋プレートは海溝から地球深部にもどってゆきます。そこで冷えたプレートどうしがこすれると地震が起こるのです。深部の熱を効率よく宇宙空間に排出するために地球が行う工夫が熱対流で、その一環として比較的浅い場所で連続的にはたらく過程がプレート運動です(深部も含めたマントル全体では大規模な上昇流や下降流[プルーム]の活動による、より間欠的な過程が支配的になります)。地球くらいの大きさだと、熱境界層であるプレートが適当な厚みになるため、プレート自身は変形せずにそれらの境界に様々な変動が集中する特徴的な造構作用が実現します。地球はプレートテクトニクスで自らを冷やす星なのです。
なんだか「暑がり」の地球が、腕をまくって涼んでいる姿が思い浮かびます。スマトラ沖地震では、表層の一部に集中した妙なこり(ひずみ)を解消できました。また全身が適度にふるえて気分もすっきりしました。表面に住む人間の都合などどこ吹く風で、地球は今さっぱりした気持なのかもしれません。このような大地震は、地球が冷え切ってしまう遠い未来まで(プレートが厚くなって沈み込めなくなる「動かない蓋」になるまで)繰り返し起こります。なんとも困ったやつですが、そこに住む我々人類には、そんな地球を正しく理解してうまくつきあってゆく知恵が必要なのでしょう。
文献・資料の紹介
さらに詳しく知りたいひとのために、文献および資料をあげておきます。地球物理学の業界紙に掲載された記事を二つ挙げます。
- ● Chao, B.F. and R. S. Gross, Did the 26 December 2004 Sumatra, Indonesia, earthquake disrupt the Earth’s rotation as the mass media have said? EOS Trans. Am. Geophys. Union, Vol.86, No.1, Jan. 4, 2005. Park, J., K. Anderson, R. Aster, R. Butler, T. Lay, and D. Simpson, Global seismographic network records the great Sumatra-Andaman Earthquake, EOS Trans. Am. Geophys. Union, Vol.86, No.2, Jan. 8, 2005.
前者ではスマトラ沖地震と地球の形や回転の変化について、後者ではスマトラ沖地震を全地球的に展開された地震計による観測という観点から論じています。
地球回転は地球物理学のなかでもとっつきにくい分野として定評(?)がありますが、最近わかりやすい教育ビデオが発売されました。
- ● 国立天文台ビデオシリーズ第6巻、イメージサイエンス制作「不思議の星・地球」、販売元:天文学振興財団(Tel:0422-34-8801)、2003年
国立天文台のビデオシリーズはすべて何らかの賞を受賞した佳作ぞろいですが、上記の第6巻はその中でも様々な賞を総なめにした「名作」で、キネマ旬報(2004年7月上旬号)でも紹介されました。
超伝導重力計による最近の発見は
- ● Nawa, K., N. Suda, Y. Fukao, T. Sato, Y. Aoyama, and K. Shibuya, Incessant excitation of the Earth’s free oscillations, Earth Planets and Space, 50, 3-8, 1998. Imanishi, Y., T. Sato, T. Higashi, W. Sun, and S. Okubo, A network of superconducting gravimeters detects submicrogal coseismic gravity changes, Science, 306, 476-478, 2004.
を見てください。最後に
- ● 「地球が丸いって本当ですか」大久保修平編著、日本測地学会監修、朝日選書、2004年5月
には、ここで解説したほとんどの話題が触れられています。







